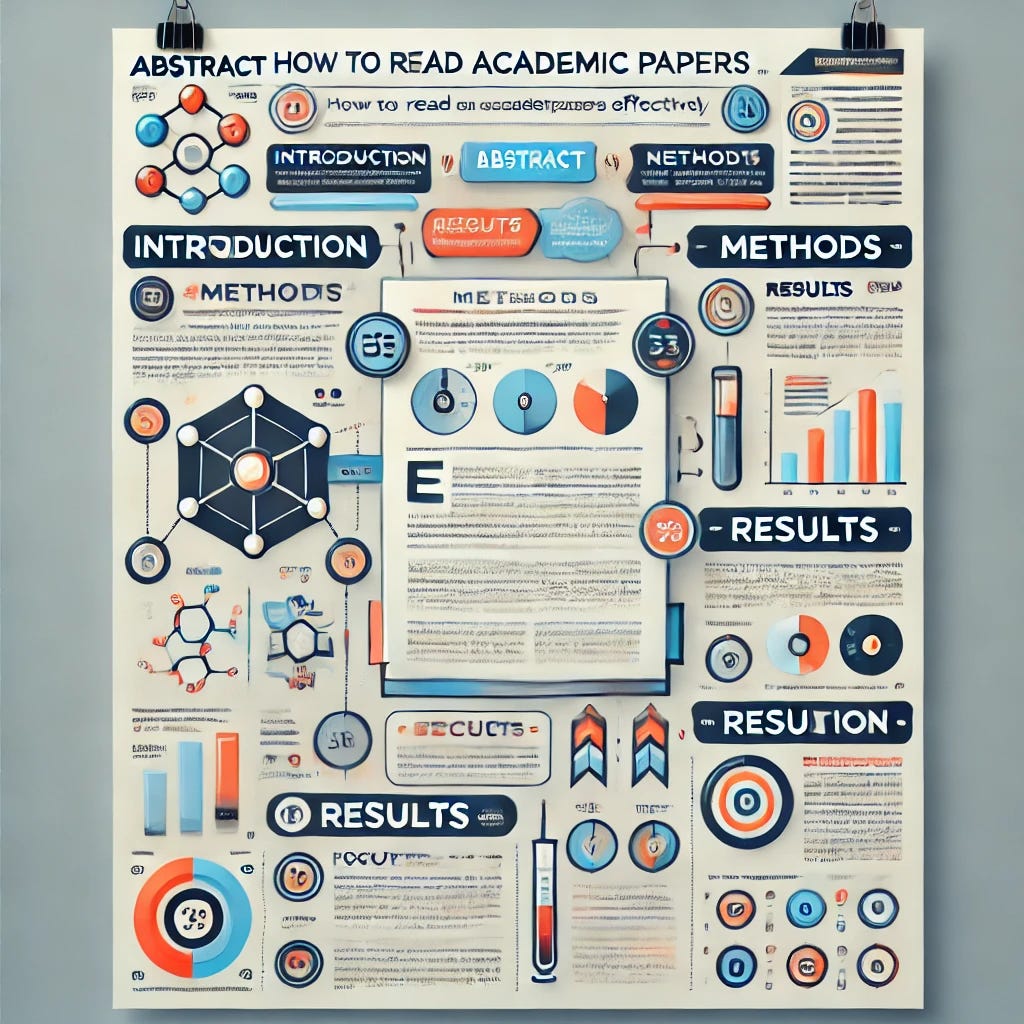論文の読み方part2: 本文編
↑こちらのAIっぽい画像、まさにAIで作っています😃
Good Morning!
自分が実践している論文の読み方を、誰でもわかるよう、超簡単に紹介するシリーズです。part2です。
「なかなか時間がなくて読めない・・」という方はとりあえず読みたい論文をダウンロードしておきましょう。30分まとまった時間があれば、3本くらいは読めるはずです。
今回は本文を読むコツです。
本文は上から読む
Abstractは「下から読む」ことがおすすめでした。
本文は「上から」読みましょう。
そもそも論文は、上から読むとわかりやすいため、あのように設計されています。
私たちが論文を書くときも、大抵上から書きます。
ですので、上から読むことが、もっとも理解を深めるのに有効な方法と言えます。
以下に、それぞれのセクションでの「読むべきポイント」を紹介します。
Introductionはknowledge gapとaimを理解する
Introductionの目的は一つ:knowledge gapの説明です。
knowledge gapとは、「何がわかっていて、何がわかっていない」ということで、これが直接「Aim: この研究の目的」につながります。
これは、論文において最も重要なポイントです。
・knowledge gapが本当に大事なgapなのか
・aimはknowledge gapに基づいているか
これだけ理解すれば、論文の70%くらいがわかったようなものです。
ここは丁寧に読みましょう。
Methodはデータの質とmeasurementの評価に
Methodは結構長いので、読み飛ばす方も結構いるかと思います。
しかし重要な点があるので、それは取りこぼさないように読みましょう:
・データの質:なんのデータを使っているか。これは簡単な場合(〇〇コホートなど)と、そうでない場合があります。そうでない場合は、そのデータが信頼できそうか(バイアスの余地がないか)、確認しましょう。
・exposureとoutcomeの定義:どのように変数を定義したかは、必ずセクションにわけられて説明されているはずです。これを確認します。例えば「がんの発症」というoutcomeが、どのように定義されているか。自己申告なのか、きちんとadjudicateされているのかで、印象は全く異なりますね。measurement errorの問題とも言えます。
statistical analysisは、resultsを読みながら確認するのがbestです。
ResultsはTableとFigureを理解するために
Resultsは、文面を追うと思考がまとまりません。
大抵大事なことはTableとFigureにまとめられているので、それぞれ見て、そこにある数値を理解する努力をします。
解析法がわからなければ、method-analysisに戻って読んだりします。
解析自体が難しい場合は、この理解に少し時間がかかることもあります。
しかし、大事なことは解析内容よりもその結果の解釈であり、結果を理解することに注力しましょう。
*統計の素養がないと、method自体の妥当性を評価することが難しい場合もありますので
Discussionはfirst paragraph
Discussionで一番大事なのは、言うまでもなく、最初の段落です。
これがsummaryになっており、キーとなる解釈が行われているはずだからです。
ここを読んで違和感があれば、resultsを読み返します。
・first paragraphを読んだ次に、conclusionを読むことが結構あります。この2つはかなり近いです。conclusionが飛躍していないか、注意して読みましょう
・次に重要な段落はlimitationです。著者らが何をlimitationとして考えているかを確認します。大抵の場合は、重要なlimitationは網羅されています。それらのlimitationがどれだけクリティカルかは、私たち読み手が判断するのです。
以上、ざっくりと本文の読み方をまとめました。
これで8-9割の論文は、15分程度で(きちんと)読むことができるはずです。
難しい論文もありますが、それは個別の話になりますし、研究者でなければそこに足を突っ込む必要はないかもしれません。
参考になりましたら幸いです。
ではまた!
***********
1/15締切の論文速読会、以下の記事より募集中です!