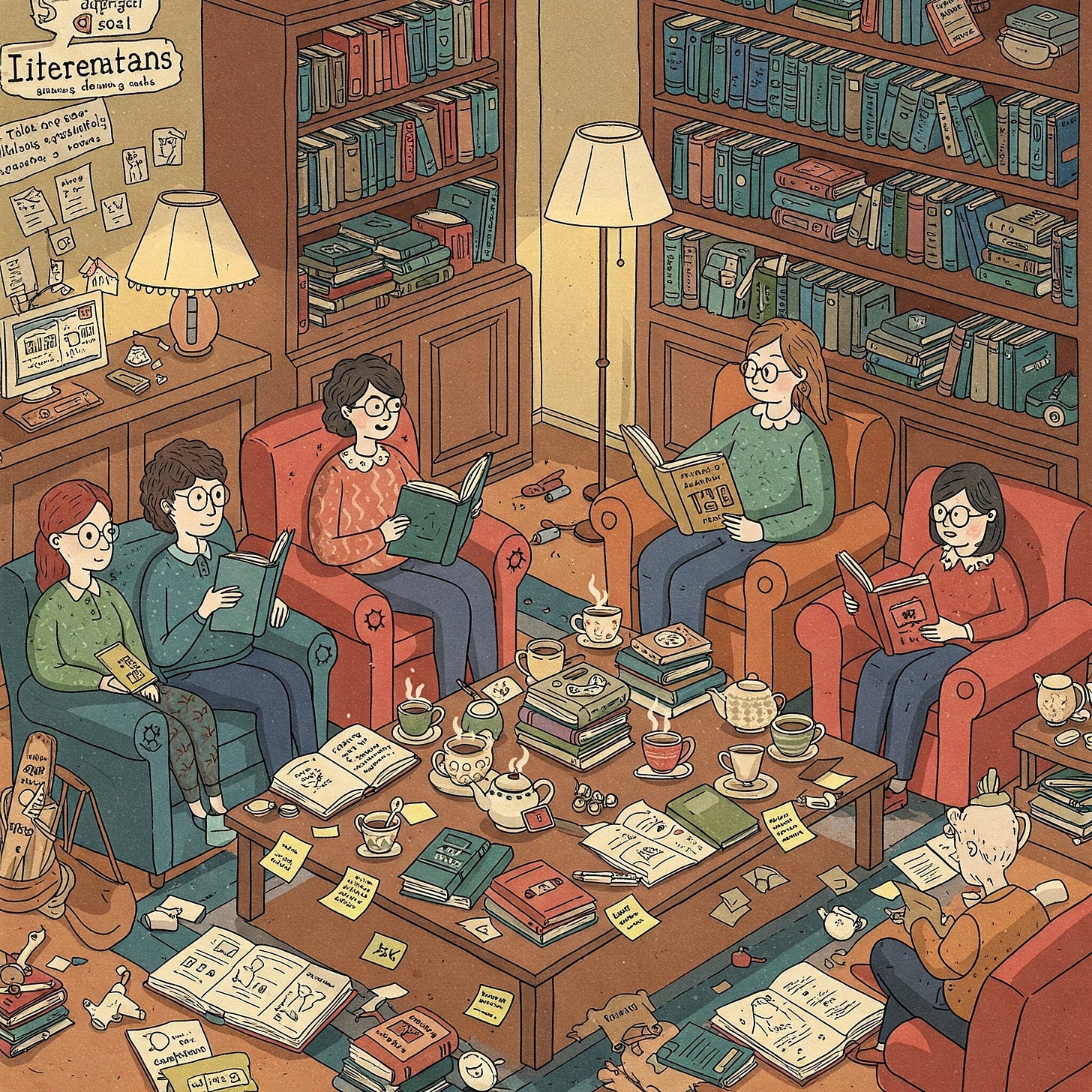【速読会】現役生からの推薦文まとめ
皆様ごきげんよう。
速読会の第1期が終わろうとしています。現役生の方が推薦文を書いて下さったので、これらを紹介していきます(書いていただいた皆様ありがとうございました!!)。
2期生まだ募集中ですので、是非こちらのリンクよりご応募お待ちしてます!
その1:看護教員の方より
はじめまして。私は地方で看護教員をしている者です。
最近参加している論文速読会について、その魅力をお伝えしたいと思います。
この会では週に1回、予防医療の有名ジャーナルから自分で選んだ論文を読み、Rik先生や仲間と一緒に学び合う場です。
思わぬ収穫がいっぱい!
論文速読会の第一の収穫は、発表という良いプレッシャーにより時間管理能力が向上し、論文を読む時間が確保できるようになったことです。発表後の達成感も格別です。Rik先生からは研究者視点での論文読解法を学び、多様な仲間との質疑応答も今では最も楽しみな時間となっています。
第二に、地方在住者にとって時間的・空間的制約のないオンライン学習の場は非常に貴重です。学生時代と異なり、自発的な学習環境の確保は容易ではありません。
最後に、期間限定の会であることで集中力が高まり、時間管理の優先順位づけと学習への意欲が強化されます。
参加する勇気が大切
初めは予防医療という分野の難しさに躊躇しましたが、「必要なら退会すればよい」という心構えで参加したことが正解でした。数か月間の活動で論文読解力が向上し、2時間で複数の論文に取り組む経験が予想以上の速読力向上をもたらしました。
最も価値があったのは志を同じくする仲間との出会いです。「学会で再会したら声をかけよう」と思える関係性を構築できました(私が勝手に思っているだけかもしれませんが💦)。
この論文速読会への参加を通じて、論文を読む楽しさを再認識しました。今後は論文執筆にも挑戦したいと考えており、この学びの姿勢を維持するために、会の継続的なサポートにも貢献したいです。
もし、本会の参加にお迷いの方がいらっしゃいましたら、ぜひ、一歩踏み出してみませんか?
その2:企業の方
今回、速読会に参加することができてラッキーでした。
でもなかなかにハードなことも確かです。
流れはこんな感じです。
金曜日夜中までに、参加者5~6名が発表する内容をクラウドにアップしてくれるので、それを土曜日の発表前にチェック。
実際に発表者5~6名が論文を見せながら、1論文15分程度で紹介する。その間、ほかの参加者は発表された内容を確認しながら、論文を追って、理解していく。
そして、最後に、質疑応答&rik先生の解説タイム!
私の場合、金曜日までに論文をまとめる、という作業が意外と大変。なんとなく理解していることを言語化して、わかりやすく伝える、というのがなかなか慣れません。
しかし、可能な限り挑戦する、という姿勢で短時間でも行うようにしています。
この作業を行うと、土曜日の皆さんへ説明しながら、自分が理解している個所、不明な個所が明確になります。そして、フィードバックを受けて、なるほどと、さらに理解を深めることができました。
次に、ほかの方の発表を聞くのも、発表する姿勢を学ぶことができました。しかも、毎週4人分程度。なかなかない機会です。そして、他の方が選ぶ論文は多くの場合、自分の視野には入らなかった論文です。そういう論文に接することで、今までにはなかった視点を得ることができます。そして、当然ですが、それらの論文に対して、他の参加者がどのような質問をするのか、そして、この研究のキモは何だったのか、を知ることもできます。
他にも書きたいことはあるのですが、もし、皆さんがこの速読会に参加されるのなら、毎週発表する機会を持つことをお勧めします。より深い学びが選べるのではないかと思うからです。また、もう一つ忘れてはいけないのは、参加しやすい雰囲気があったことです。人前で発表するのが苦手な私でも、今回、思い切って参加してよかったです。
4週間予定を調整するのは大変かもしれませんが、得られる満足感は大きいと思います。そして、それはその4週間後も続くと思います。
その3:産業医の方
論文を毎週速読するという会です。結論から言うと参加して本当に良かったです。
以下にメリットを示します。
1 インパクトファクターが大きい論文に触れることで、「良い研究とは何か」が分かる。
インパクトファクターが大きな論文(Lancet、NEJM、JAMAなど)ではこのような方法が使われて研究がおこなわれているのだということが分かる。一方、イケてない論文もわかる(意外とこのレベルのjournalに載る論文でもこのようなからくりや、弱みがあるのだな、など・・・)。
2 論文の内容を把握することが難なくできるようになる。毎週読むから英語のreading能力が付く。
批判的吟味を行うにはもっと勉強しないといけませんが、その土台がこの速読会で培われたと思います。また英語を読むのが(前よりは)苦ではなくなりました(でも生成AIもたくさん使ってます)。
3 rik先生のコメントや他の参加者のコメントでさらに勉強になる
自分で読むだけでは流してしまうところも、rik先生のするどいコメントと他の参加者の視野も借りることでさらに論文の背景を深堀することができました。
みんなでオープンに、論文に対するディスカッションができる「心理的安全性」があるのがこの会の良いところでした。しいて言うとデメリットは、論文のコラムを準備するのにちょっと負担がかかることですが、みんなで切磋琢磨すれば乗り越えられます。
さあ、あなたも論文速読してみませんか?
その4:総合診療医の方
今回予防医療の領域の論文速読会に参加させていただけて本当によかったと感じていますので内容を共有させていただきます。
予防医療に関するビッグジャーナルに掲載されている論文を対象に毎週土曜日午前2時間の抄読会です。
ざっと思いつくよかった点を列挙します。
毎週1本人に発表できるレベルで論文を読み込む機会が強制的に作られる
興味がある論文を流し読みすることはあっても、人に発表するレベルとなるとやはり読み込み方は変わります。先行研究に目を通したりmethod, resultをじっくり読み込んだり労力はかかりますが、段々と体力もついてきて理解するのに要する時間や負担感が減った体感があります。また参加する前にはなかった着眼点、批判的吟味の仕方が備わりました。
他の人からのコメント
自分の中にはなかった視点からのコメントや質問から得られる学びがあります。
Rik先生の解説
これが一番と思っていますが、デザインの不備、結果の解釈、コンテキスト、予防医療界隈での位置付けなどなど第一線でご活躍されているrik先生からのコメント・解説は本当に学ことが多いです。これは言葉では説明しきれないので是非ご参加いただき体感してください。
他の人の発表
そもそも自分が目を通さない分野の発表がほとんどなのでとても新鮮な気持ちで発表を聞くことができます。そして発表を聞きながら同時に論文を読み込んでいくのでまさに速読を行います。その人の解釈も勉強になりますし、質問・コメントからもたくさんの学びを得られます。
少なからず時間を割くことにはなります。ですがそれを負担ではなく良い機会と捉えて積極的に発表するためのトレーニングと感じられる方にはこの上ない機会だと思います。
その5:大学教員の方
ここでは、毎週2時間、5本程度の論文を抄読し、ランダム化比較試験(RCT)、コホート研究、メタ解析といった研究デザインを題材に、楽しく学んでいます。さらに、ターゲット・エミュレーション(Target Trial Emulation)といった解析手法も取り上げ、エビデンスをより実践的に理解できるようにしています。
私は、コホート研究で、RCTが難しい場面での因果推論の工夫として、ターゲット・エミュレーションの考え方を学びました。「観察研究から、まるでRCTのような推論を導き出すには?」という視点で論文を読み解き、研究の面白さがぐっと増しました。
論文を正しく読み、研究デザインの意図を理解すると、エビデンスの見方が大きく変わります。研究をより実践的に学びたい方におすすめです!
熱いrik先生のコメントもお見逃しなく!
その6:産婦人科医師の方
本会は、予防医療・医学に関する一流誌の原著論文を毎週速読し、参加者で当該論文の批判的
吟味を行う会です。
本会のメリットは下記でしょうか。
1.いわゆるインパクトファクター(IF)が高い論文(ほとんどはRCTデザイン)に触れることで、予防
医療・医学領域の研究の現時点における到達点がわかる。
2.たとえ、高IFに載るRCTデザインの論文であっても、必ず限界点があり、その限界を克服するた
めに次の研究にどうつなげていけば良いのかを把握できる。
3.1人では見逃しがちなことも、10人の参加者の誰かから気づきを得れる。
4.(元 東大教員の立場からですが)、これから東大や京大などの公衆衛生大学院を受験される
方々には、当会に参加することで、他の受験者に比べて、かなり大きなアドバンテージを得れるは
ず(英語、専門記述式、小論文対策など)。
5. デメリットは、あまり思い浮かばないが、主催者たるRik先生の本(極論で語る予防医療)は、読
んで参加された方がより良い(現、第1期生も必読かと)。
なお、各論文の臨床統計上の議論は、あまりないので、各自の自助努力は必要だろう。
いずれにせよ参加して損はない「速読会」だと思います。
最後に
2時間で6本も論文を読む、というのは「無理だろ」と思われる方が多いかと思います。
しかし速読会では、これが可能であることと、その教育効果が高いことを実証してきました。
是非皆さんと一緒にできれば嬉しく思います!!
ではまた。